こんにちは、HIROです。皆さんは、和太鼓のチームを作りたい。なんて思った方はいますか?
高校の部活動で和太鼓をやっていて、卒業後、大学でも続けていきたいけど、大学に和太鼓部がない!ですとか、
部活の仲間たちと共に和太鼓を続けていきたい。ですとか、学校や就職のタイミングで新しい地に行っても太鼓を続けたい!
そんな熱い想いを持っている方はとても参考になる記事になっています。

はじめに
和太鼓のチームを立ち上げたい。そんな方が、この記事を読んでいただけることに感謝したします。
私も、大学生時代に和太鼓のチームを実際に立ち上げて運営してきた過去があります。
今回の記事は、その頃の体験談も踏まえながら進めていきます。
和太鼓のチームを立ち上げるには、人・環境・機材
この3つが揃えばすぐにでも始めることが出来ます。
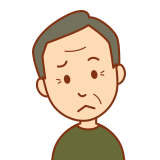
確かに、それがあれば出来そうだけど実現するのは難しいんじゃないの?
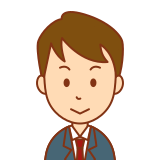
もちろん、状況によって難しいこともあるかもしれませんが、
大丈夫!1つ1つクリアにしていけばきっとできるようになります!
和太鼓チームを立ち上げよう①〜環境を作ろう〜
和太鼓チームを立ち上げる際に必要な要素が3つありました。
人・環境・機材
この3つについて解説していきます。
まず、はじめにとりかかるのが、「環境」を作ることです。
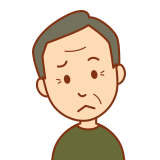
え?、まずは人を集めることからじゃないの?
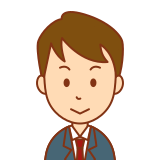
もちろん、人集めも大切ですが、環境を作ることから始める方が良いことが多いです。
どうして、環境からなのか、解説していきますね。
他の団体を立ち上げるのであれば、人(仲間)を集めることが、一番最初に取り組むべきことでああります。
しかし、和太鼓のチームを作るにあたっては、「環境」を作ることが最も難しく、時間がかかる為一番最初に取り組む必要があります。
では、なぜ環境を作ることが難しいのか?
近年のニュースでも度々話題になりますが、近所の騒音トラブルによる事件が発生していたり、
新型コロナウイルスの影響による、巣ごもり需要の増加で益々、音に対する配慮が必要な世の中になっています。
その中でも、和太鼓は音に加えて振動を発する楽器であるために、世間からの風当たりが一層冷たくなっています。

和太鼓の環境づくりとしては、練習する場所の確保をすることが最も大変なことになります。
現在、和太鼓団体の活動場所として、以下の施設で行なっていることが多いです。
- 学校
- 公民館等公共施設
- 音楽スタジオ
- 外(河川敷や高架下など)
これは、アマチュアに限ったことではなく、プロ和太鼓奏者や団体でも当てはまります。
和太鼓チームを立ち上げる場合、以上の場所に実際に赴き、和太鼓ができる環境か
施設を運営している方に相談してみましょう。
学校や公共施設であれば、場所を使用する代金も比較的安価で済む場合が多いですが、
周囲の環境によっては、断られるケースも存在しています。
外の場合は、市役所や警察署で許可が必要になってきますが、
基本的には車での機材運搬が必要な上に天候に左右されてしまうので、
団体の主な活動場所としては室内を選択することがおすすめです。
すでに、和太鼓での活動に理解があったり、他の和太鼓団体が使用している施設であれば
割と簡単に活動の拠点とすることが可能ですが、地域や学校での和太鼓団体が少ない場合は、
根気よく施設を巡って、相談を重ねていく必要があります。
実際に和太鼓の利用が可能になったら少人数でも良いので、利用してみましょう。
使ってみてからわかることがたくさんあります。
例えば、使用する施設内の音の反響具合によっては、太鼓を打つたびに
振動によって余計な音が鳴り、集中力が削がれてしまう。ということもあったりします。
環境が整えば、団体として活動出来る第一歩が踏み出せるかと思います。
和太鼓チームを立ち上げよう②〜仲間を集めよう〜
和太鼓の環境が整ってきたら、それと並行して人を集めなければいけません。
ただ、闇雲に人を集めても問題はありませんが
和太鼓の団体として活動していくにあたってのコンセプトを明確にしておくと
よりよく活動ができるので、あらかじめ決めておくことをおすすめします。
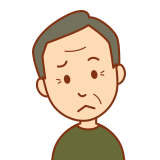
チームのコンセプト?それを考えたこともなかったけど・・・
どんな風に考えればいいの?
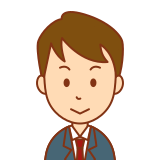
チームのコンセプトは活動の軸になってくる考え方に
なるので、予め考えてから始めるといいと思います。
イメージとしては、企業の「求める人材」といったところでしょうか。
和太鼓チームのコンセプトは様々あります。
例えば、一打一打の音にこだわる。とか、日本の伝統楽器である和太鼓を守っていきたい。とかですね。
そういった方針を持つチームを作り上げようとすると、
自ずとそのコンセプトにあった人もしくは、そのコンセプトに合わせることができる人を
集めることで、和太鼓の団体としてより成長し続けることが出来ます。
この業界でも、チームを立ち上げようとして挫折した和太鼓奏者、
チームを作り上げても志なかばで解散。というようなチームがいくつもあります。

では、そのコンセプトに合った人材をどのように集めるのが良いのでしょうか?
和太鼓団体に限ったことではありませんが、人を集めるには3つのステップが必要になります。
- 1.窓口を作る
- 2.発信する
- 3.対応する
それぞれについて説明します。
1.窓口を作る
実際に一緒に活動してくれる人が、あなたと繋がることが出来る「窓口」を作ることを一番はじめに行なってください。
私の経験上、以下の4つの窓口を作れば問題ありません。
- SNSアカウント
- メール
- 電話
- HP
SNSアカウントは、Twitter、instagram、Facebook、この3つもあれば充分です。
個人アカウントではなく、団体の専用アカウントがあると良いでしょう。
DMなどでのやり取りまで出来るようになっていれば、若い世代を集める窓口としては一番良い方法です。
メールは、yahooがやGmailなどの、フリーメールを1つ作っておきましょう。
SNSの個人アカウントを知られたくない・持っていない場合や、公的な企業等からの演奏依頼などは、
メールでのやり取りが多いので、団体専用のアドレスを作っておくと、非常に便利です。
電話は団体専用の電話を作ることは非常に難しいです。
チームの立ち上げの場合は誰かの電話で代用することになるケースが多いのですが、
直接のやり取りには電話を使用するので、無ければならないものの1つになります。
団体のHPはあると非常に便利です。不特定多数の方に向けてSNSと絡めて宣伝活動を行うことができます。
SNSでは少ない情報を伝えるのには便利ですが、しっかりとした情報を伝えることが難しいので、
興味を持ってくれた人に、しっかりと情報を伝えることが出来ます。
昔はホームページを作成するには、HTMLの知識がないと作ることが出来ませんでしたが、
現在は、無料でホームページを作成する事が出来るので、ぜひ!作成してみる事をお勧めします。
2.発信する
上記の4つの窓口を作ることが出来たら、それぞれの窓口から積極的に発信していきましょう。
発信はSNSが一番簡単ですが、集めたい人(顧客)に合わせて使用媒体を工夫しましょう。
チラシを作って配布したり、簡単な体験イベントを行なったりする事も有効な手段ですね。
チームを立ち上げる段階では、様々な情報を発信してより多くの人に知ってもらうことが必要になってきます。
和太鼓に興味がある人はどの世代でも必ずいます。他のスポーツや芸術分野に比べると決して数が多いとは言えませんが
チームのコンセプトに合った人が必ず現れるので、諦めずに積極的にいろんな情報を発信していきましょう。
3.対応する
実際に話を聞きたい人やチラシやホームページを見てくれた方が連絡してきたら真摯に対応しましょう。
この人はどういう人なのか。不安なことはないのか。など、積極的なコミュニケーションをしてみましょう。
特に最初の1人目がとても重要です。何もない所に飛び込んでくれるのはとても勇気がいることなので、
人によってはプレッシャーに感じてしまいます。その不安を取り除くように努めましょう。
次回は最後の要素「機材」について説明します。
コメント